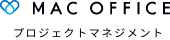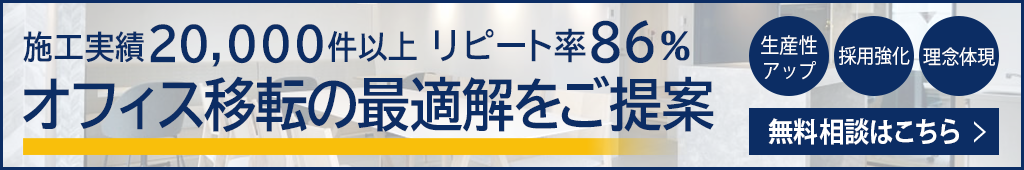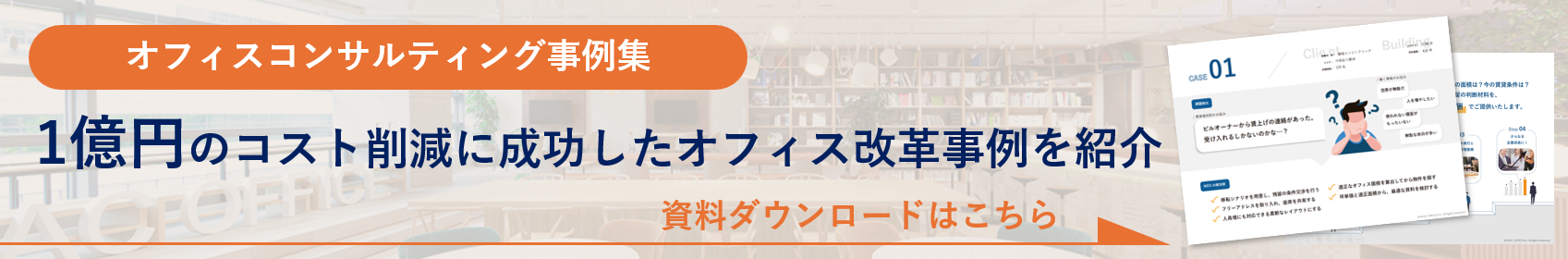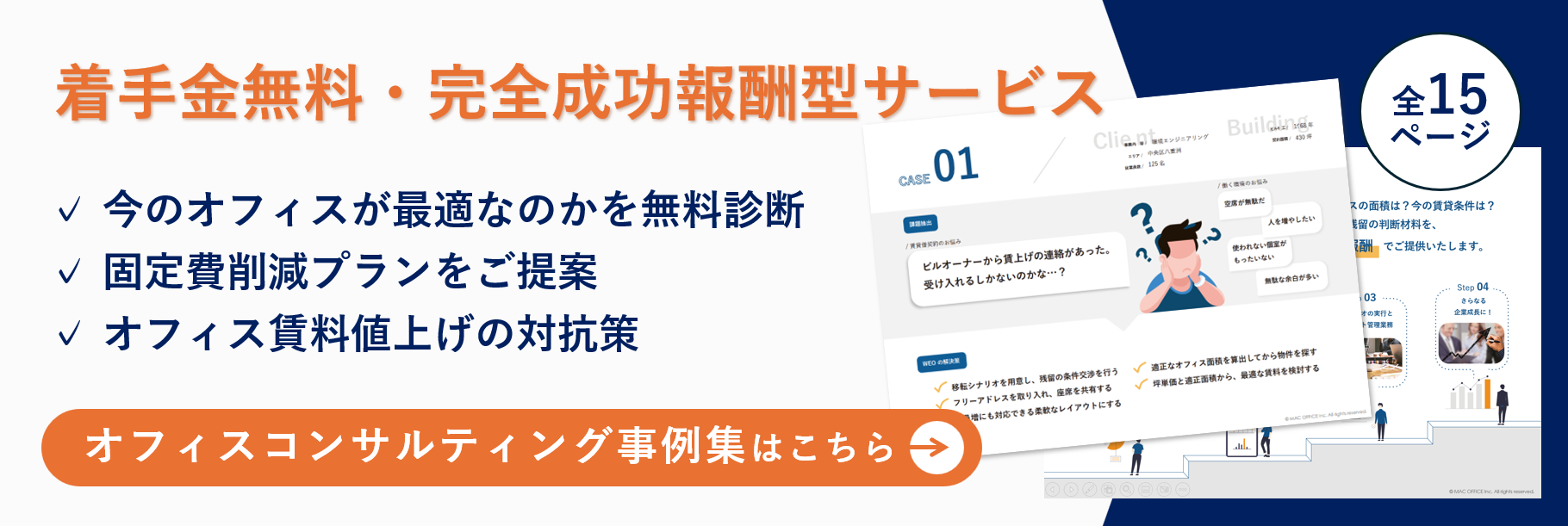新リース会計基準の内容が難しく、対応に不安を感じていませんか。新リース会計基準は、2027年4月に強制適用される新しい会計基準のことです。今回は新リース会計基準に関して、企業が押さえるべき変更点や準備すべき対応を解説します。
※2025年5月時点の情報です。
新リース会計基準の概要

新リース会計基準を正しく理解するためには、従来のリース会計との違いや今回の改正で何が変わったのかを把握する必要があります。
ここでは基本的な考え方から対象範囲・適用時期について、新リース会計基準の概要について解説します。
そもそもリース会計基準とは?
リース会計基準とは、企業が行うリース取引において、どのように会計処理を行うかを定めたルールのことです。
建物や車両・設備などの資産を一定期間借りて使用する「リース取引」では、使用料にあたるリース料をどのタイミングで、どの勘定科目で処理すべきかが問われます。
現行の基準では、「ファイナンスリース」と「オペレーティングリース」の2種類に分類されます。
| 名称 |
内容 |
| ファイナンスリース |
リース期間中に契約を解除できず、借手がリース物件の取得価格や関連費用のほぼ全額をリース料として支払うもの |
| オペレーティングリース |
ファイナンスリースの条件に該当しないリース取引 |
新リース会計基準により何が変わる?
2024年9月、企業会計基準委員会(ASBJ)は「リースに関する会計基準」などの改正を公表しました。
これにより、これまで費用処理されていた多くのリース取引について、原則すべてが貸借対照表に資産・負債として計上される方向へと変更されました。
出典:企業会計基準委員会(ASBJ)「企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」等の公表」
主な変更点は、従来は損益計算書上で費用として処理されていた多くのリース取引が、貸借対照表に資産・負債として計上されるようになったことです。
具体的には、複合機のレンタルやオフィスの賃貸借契約といった従来オペレーティングリースとして費用処理されていた取引も、原則としてオンバランスでの処理が求められます。
これにより、国際会計基準(IFRS)との整合性が図られ、リース取引の会計処理における国際的なギャップが縮小することが期待されています。
新リース会計基準の適用対象は?
新リース会計基準の適用対象となるのは、主に金融商品取引法の適用を受ける企業です。具体的には、下記のような企業が該当します。
・上場企業およびその子会社や関連会社
・資本金5億円以上または負債総額200億円以上の大会社
・会計監査人を任意で設置している企業
・指名委員会等設置会社
・監査等委員会設置会社
上記に該当しない中小企業については、「中小企業の会計に関する指針」に従って従来の会計処理を継続することが認められています。
企業ごとに求められる対応レベルが異なるため、自社がどの区分に該当するか、早めに確認しておくことが重要です。
新リース会計基準の適用開始時期はいつから?
新リース会計基準は、2027年4月1日以後に開始する連結会計年度および事業年度の期首から適用されます。
ただし、企業の判断により、2025年4月1日以後に開始する会計年度から前倒しで導入することも可能です。
新しい基準は、会計年度の途中や終了時点からではなく、必ず年度の開始日から適用しなければなりません。
初年度には、原則として遡及適用(過去にさかのぼって処理する方法)が必要です。しかし、前年と比較して数字を直さず、差額だけを期首の利益剰余金に反映する方法も認められています。
また、どの経過措置を使うかによって、初年度の利益剰余金が大きく変わる可能性があるため、慎重な対応が求められます。
新リース会計基準導入による企業への影響

新リース会計基準の導入は、会計数値だけでなく経営や業務全体にさまざまな影響をもたらします。ここでは、新リース会計基準導入による主な企業への影響について解説します。
「財務諸表」への影響
新リース会計基準の導入により、使用権資産とリース負債が貸借対照表に計上されることになります。
その結果、総資産および総負債が増えるため、特にリースを多用している企業では自己資本比率やROA(総資産利益率)の低下など、指標に影響が及ぶ場合があります。
また、損益計算書では、これまでまとめて「リース料」として処理していた費用が、「減価償却費」と「支払利息」に分けて記載されるようになります。その結果、営業利益の数値が従来とは異なり、変動が生じる点に注意が必要です。
財務数値の見方が変化するため、社内外の関係者に対しての説明や適切な注記対応が求められるでしょう。
関連記事:「財務諸表分析の方法は?重要性も解説」
「経営判断」への影響
資金調達や設備投資といった意思決定の場面にも、新リース会計基準は大きく関係してきます。
これまで「購入」と「リース」で会計処理が異なっていたため、処理方法の違いが調達方法の選定に影響していました。
しかし、新基準では両者の差が小さくなるため、事業戦略や運用コストといった観点を重視して判断できるようになります。
例えば、資金調達のしやすさや保守メンテナンスの対応・廃棄コストの有無など、より本質的な経営要素に基づいて意思決定が可能です。
制度変更により、戦略的な経営判断が可能になる点は、多くの企業にとって大きな意味を持つでしょう。
関連記事:「中期経営計画の作り方|作成時の注意点や軌道に乗せるためのポイントも解説」
「業務プロセスやシステム」への影響
会計処理にとどまらず、業務プロセス全体にも影響を与えるのが、新リース会計基準への対応です。
導入にあたっては、リース取引の有無を見極める判断や、新しい基準に適合する経理フローの再構築が必要になります。
契約管理の強化やリース期間の見積もり・割引率の設定など、これまで以上に高度な情報管理と専門的な判断が求められます。
こうした対応を進めるには、経理部門と契約部門の連携強化に加えて、既存システムの見直しや新たな会計システムの導入も視野に入れる必要があるでしょう。
新リース会計基準適用に備えて企業が準備するべきこと

2027年4月の新リース会計基準適用に向けて、企業は業務体制や会計処理の見直しを進める必要があります。ここでは、新リース会計基準適用に備えた具体的な準備項目を4つ紹介します。
対象となる取引を特定する
まず必要となるのが、自社で締結しているリース契約や賃貸借契約の洗い出しです。
新リース会計基準では、資産や負債として貸借対照表に反映される可能性があるため、対象となる取引を明確にする必要があります。
契約書の記載内容や契約期間、リース料の支払い条件などを丁寧に確認し、該当する取引を正確に把握しましょう。
こうした基礎情報の整理は、後の会計処理やシステム対応の土台となります。まずは契約書の内容を確認し、対象範囲を整理する作業から始めましょう。
影響額を算定し、自社の方針を検討する
洗い出した取引が新リース会計基準の適用対象となる場合は、資産・負債としてどれだけの金額が計上されるか、また損益への影響がどれほどかを試算します。
その結果をもとに、簡易的な処理で良いのか、重要性の観点からどのように対応するかといった、自社にとってベストな方針を検討します。
決定した方針は、将来的な社内外への説明に備えて、記録として文書化しておくと良いでしょう。
新リース会計基準に則って経理規程を改訂する
会計方針を決定したあとは、役員への最終報告を経て、自社の経理規程を新リース会計基準に合わせて見直します。
基準に沿った規程を整備することで、会計処理の統一性と実務上の正確性が確保され、社内運用のブレを防げます。規程の改訂は、基準適用後の混乱を防ぐためにも早めに取り組んでおくと安心です。
システムや各種資料を改修する
経理規程の内容に基づき、社内システムや関連資料も整合性を保つよう見直す必要があります。
例えば、リース債務の計上に対応できるよう、固定資産システムやリース管理用のExcelファイルを更新します。
また、取締役会に提出する月次資料や、財務諸表作成用のテンプレートも必要に応じて調整しましょう。
こうした準備を通じて、実務での運用ミスや対応漏れを防ぐ体制を整えていくことが、新リース会計基準適用に備えて必要になります。
まとめ
新リース会計基準は、財務諸表や経営判断・業務プロセスに広く影響します。2027年の強制適用に備え、対象取引の特定や影響額の試算・経理規程・システムの見直しなど、段階的な準備が不可欠です。企業を安定的に運用するためにも、早めに対応を進めましょう。
関連記事:「損益分岐点を算出するには固定費と変動費の分類が重要|損益分岐点を下げる方法も紹介」
 経営戦略
経営戦略
 経営戦略組織づくりオフィス戦略
経営戦略組織づくりオフィス戦略
 経営戦略オフィス戦略
経営戦略オフィス戦略
 経営戦略オフィス戦略
経営戦略オフィス戦略
 経営戦略
経営戦略
 経営戦略
経営戦略