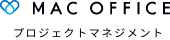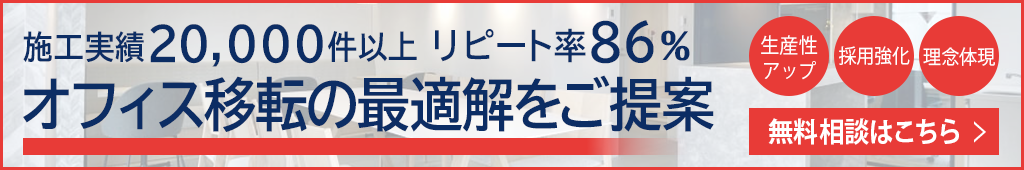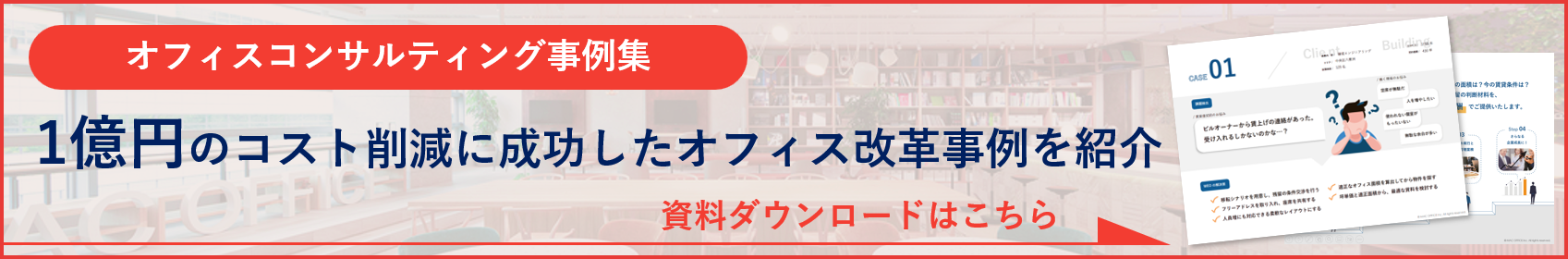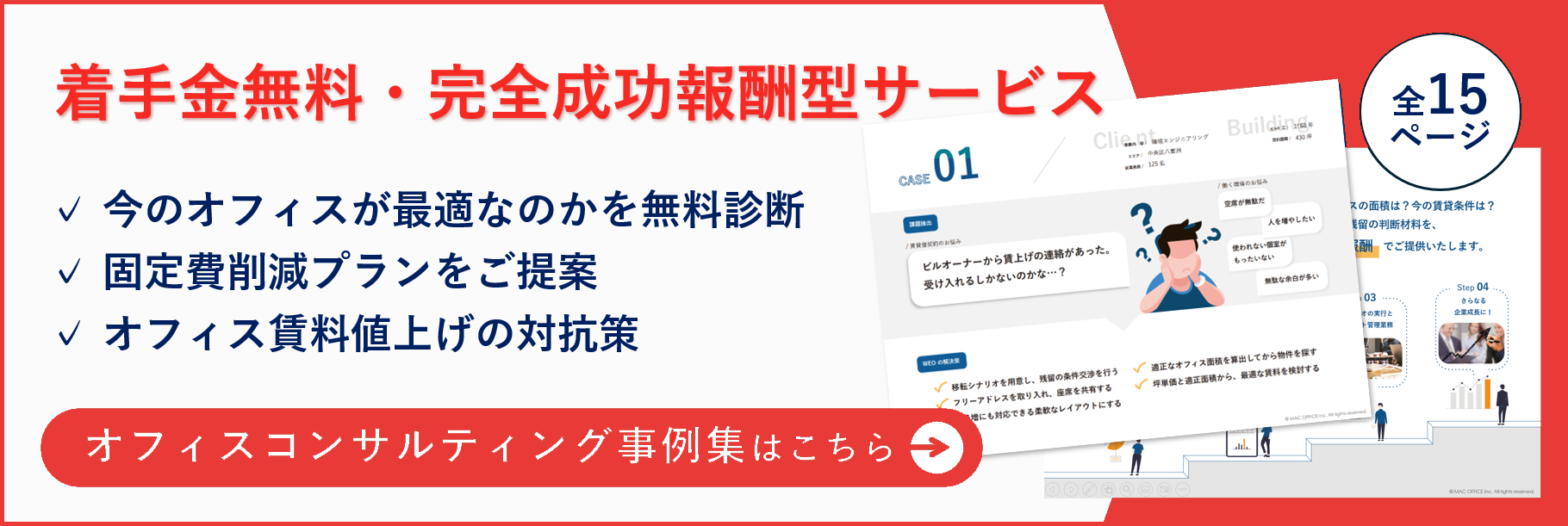企業が安定して事業を続けるためには、災害や事故、感染症などの非常事態に備える「BCP(Business Continuity Plan=事業継続計画)」が欠かせません。しかし、策定しただけでは状況の変化に対応できず、実効性が低下してしまいます。事業環境や組織体制の変化に合わせ、定期的に見直すことで、非常時でもスムーズな対応が可能です。今回は、BCPを見直すべきタイミングやポイント、オフィス戦略との関係について解説します。
BCP見直しに適した時期とは

BCPは策定したら終わりではなく、事業環境や社会情勢の変化に合わせて定期的に見直す必要があります。特に、防災訓練や経営方針の変更、自然災害の発生など、重要な出来事があった際は内容の更新を検討しましょう。
防災訓練の実施時
防災訓練は、策定済みのBCPが実際の現場で機能するかを確認する重要な機会です。訓練では、従業員の安否確認や指定された避難場所への移動など、災害発生直後の行動手順を実践します。
この過程で、想定していなかった課題や連絡体制の不備が明らかになることも多く、改善点を洗い出すきっかけとなるでしょう。
定期的な訓練を通じて内容を検証・更新し、より実効性の高いBCPに仕上げることが重要です。
経営方針の変更時
新商品や新サービスの提供、新規事業の立ち上げなどで事業内容や経営方針が変わると、事業リスクや重要業務の優先度も変化します。
そのため、既存のBCPが現状に適しているかを再確認しなければなりません。特に、供給ルートや人員配置、業務フローに変化がある場合は、緊急時の対応計画にも影響が及ぶため、速やかな見直しが重要です。
関連記事:
「中期経営計画の作り方|作成時の注意点や軌道に乗せるためのポイントも解説」
「新規事業立ち上げが重要な理由とは|流れや成功させるコツも解説」
自然災害・感染症などの発生時
地震や台風などの大規模災害、また新型感染症の流行など、事業運営に大きな影響を与える事態が発生した場合は、BCPの即時見直しが必要です。
災害や感染症は、従業員の出勤体制やサプライチェーンの維持、顧客対応など多方面に影響を及ぼします。被害状況や社会情勢の変化に合わせて計画を修正し、現場で実行可能な体制を整えることで、事業の早期復旧と継続を確保できます。
法改正時
法改正が行われた際には、その内容を速やかにBCPへ反映しなければなりません。規定や手続きを旧制度のまま運用し続けると、意図せず法律違反となる可能性があります。
特に業務手順や対応フローに関わる改正があった場合は、速やかに計画を見直し、実際の運用と整合性を取りましょう。
組織体制の変更時
人事異動や配置転換により、従業員の勤務地や連絡先が変更された場合は、BCPの連絡網や対応体制を更新しなければなりません。
連絡先や役割分担が古いままだと、災害時の情報伝達や安否確認に支障をきたすおそれがあります。また、新卒や中途で多くの人員を採用した際も、連絡先の登録や緊急時の行動手順を見直し、全員が迅速に行動できる体制を整えることが重要です。
関連記事:「組織改革のタイミングや成功のためのフレームワーク・進め方とは」
BCPを定期的に見直すメリット

BCPを定期的に見直すことで、事業環境の変化や新たなリスクにも柔軟に対応できます。最新の状況に合わせた計画は、緊急時の対応力を高め、事業の継続性を強化するでしょう。
顧客や取引先、求職者からの信頼向上
BCPを策定し、定期的に見直すことは、顧客や取引先から「リスク管理が行き届いている企業」という評価を得ることにつながります。
緊急時にも事業を継続できる体制が整っていると認識されれば、信頼感が向上します。また、従業員にとっても安心して働ける環境と映るため、求人への応募促進にもつながるでしょう。
従業員の安全確保
BCPを定期的に見直すことで、災害や事故発生時に迅速な安否確認が可能となり、従業員を怪我や危険から守る体制を維持できます。
平常時から避難経路や連絡手段を明確にしておけば、緊急時の混乱を防ぎ、安全性の高い職場環境の構築にもつながるのです。
被害や損失の軽減
BCPを適切に策定・更新しておけば、緊急時に迅速かつ的確な初動対応が可能となり、経営へのダメージを最小限に抑えられます。
平常時からリスクを洗い出し、具体的な対応策を準備しておくことが重要です。そうすれば、被害の拡大を防ぎ、サプライチェーンの維持にもつながるでしょう。
BCPを見直す際のポイント

BCPを効果的に維持するためには、単に更新するだけでなく、重要な観点を押さえて見直すことが大切です。ここでは、見直し時に注目すべき主なポイントを紹介します。
定期訓練によりブラッシュアップする
BCPは策定して終わりではなく、定期的な訓練を通じて精度を高めていきましょう。訓練は、事前に目的を明確に設定し、実際の運用を想定して実施します。
その過程で浮かび上がった課題は、関係部署と共有し、運用・システム・ツールなどの項目ごとに整理して改善につなげることが重要です。
定期的なサイクルを継続していけば、実効性の高いBCPへと進化させられます。
課題に優先順位をつける
BCPを見直す際に課題が複数見つかった場合は、重要度や緊急度に応じて優先順位をつけることが欠かせません。
まずは、事業を取り巻くリスクを洗い出し、それぞれを分析・評価します。その上で、事業継続に大きな影響を及ぼす可能性が高い課題から順に対応していきましょう。
優先順位をつければ、限られた時間や資源を効率的に活用し、実効性の高い改善につなげられます。
運用体制を確認する
BCPを効果的に機能させるには、策定した対策を実行に移すための運用体制を明確にしなければなりません。
具体的には、各対策の担当者や実施期限を決定し、実行計画として整理します。計画を作成した後は、次回の定期訓練時に内容を検証し、必要に応じて修正を加え、BCPの精度を継続的に高めていきましょう。
実用性の高いマニュアルを作成する
BCP発動時に迅速な行動を取るためには、実用性の高いマニュアル作成が欠かせません。内容が複雑で分量が多すぎると、必要な手順を探すのに時間がかかり、対応が遅れる可能性があります。
そこで、チェックリストやフローチャートを活用し、重要な行動や判断の流れを簡潔かつ視覚的に整理するのが有効です。シンプルさを心がけ、緊急時でも迷わず行動できるマニュアルにしましょう。
BCPを意識したオフィス戦略とは
BCPを踏まえたオフィス戦略では、災害時の事業継続を意識したビル選定やレイアウト設計、テレワーク環境の整備が重要です。ここでは、その具体的なポイントを解説します。
ポイント1|ビルの耐震性能の確認
オフィス移転や新設の際は、建物の耐震性能を必ず確認しましょう。特に新耐震基準を満たしているかどうかは最低限のチェック項目です。
さらに、地震の揺れを直接受け止める「耐震構造」、揺れを吸収して被害を抑える「制震構造」、揺れそのものを建物に伝えにくくする「免震構造」など、構造ごとの特性を理解して選定します。
| 構造 | 特徴 |
| 耐震構造 | 基礎や柱などの構造体を強くし、接合部分を丈夫なもので固定・補強することで、地震の揺れに耐える |
| 制震構造 | 振動を軽減させる「ダンバー」などを構造に組み込み、揺れを吸収する |
| 免震構造 | 建物と地盤の間に免震装置を設置し、揺れを遮断する |
ポイント2|非常用電源の確保
災害や事故による停電は、業務の継続に大きな支障を与えます。そのため、非常用発電機や蓄電池など、停電時でも一定時間稼働できる電源設備が備わっているかを確認しておくことが重要です。
特に、サーバーや通信機器など事業継続に欠かせない設備が停止しないよう、必要な容量と稼働時間を事前に把握しておきましょう。
また、設置されている非常用電源が定期的に点検・整備されているかも確認し、いざという時に確実に稼働できる体制を整えることが求められます。
ポイント3|周辺環境の確認
自治体が公開しているハザードマップを活用し、洪水・地震・土砂災害の危険エリアに該当しないかを把握しましょう。
地形や道路状況も含めて総合的に評価し、緊急時に避難や物資輸送が円滑に行える立地を選定するのが望まれます。
ポイント4|防災対策
災害発生時に迅速な避難が可能となるよう、複数の避難経路や非常階段の有無をチェックしましょう。
さらに、火災への初期対応に不可欠な消火設備の設置状況や、長期停電・物流停止に備えた防災備蓄品の充実度も評価ポイントです。
防災体制が整ったビルは、従業員の安全確保と事業継続の両面で大きな安心材料となります。
ポイント5|感染症対策
オフィス選定時には、空調や換気設備の性能が感染症対策として十分かを確認しておくことが大切です。適切な換気システムは、空気中のウイルスや細菌の拡散を抑える効果があります。
さらに、自動扉や顔認証システムなどを活用した非接触環境を導入すれば、接触による感染リスクを減らせるでしょう。
ポイント6|家具・什器の固定
地震発生時の被害を抑えるためには、家具や什器、OA機器を壁や床にしっかり固定し、転倒防止対策を講じることが重要です。
固定が不十分な場合、倒れた家具が避難経路を塞いだり、従業員の怪我につながったりするおそれがあります。
特に書庫や大型キャビネット、複合機などの重量物は、耐震金具やストッパーを用いて安全性を確保しましょう。
ポイント7|リモート勤務体制の整備
リモート勤務体制を整えておけば、感染症の流行や自然災害による交通機関の停止時にも業務を継続できます。
必要なツールや通信環境を事前に整備し、社員が自宅やサテライトオフィスから安全に業務を行える仕組みを構築するのが大切です。
また、オフィス勤務とリモート勤務を併用するハイブリッドワークを採用すれば、柔軟性と事業継続性を両立できるでしょう。
関連記事:「ハイブリッドワークとは|メリットや導入時のポイント、成功事例を紹介」
ポイント8|複数拠点への分散
事業の拠点を複数に分け、どちらでも同等の業務が遂行できるように設備や人員を整備しておけば、災害や感染症の影響による事業停止リスクを軽減できます。
本社から距離を置いた場所にサテライトオフィスを設ければ、被害が一方の拠点に集中するのを防げるでしょう。
関連記事:「サテライトオフィスとは?特徴やメリット、開設時の注意点などについて解説」
BCPを意識したオフィス戦略の相談なら
BCP対策を含め、経営課題に応じたオフィス戦略なら、MACオフィスの「WEOマネジメント」をご活用ください。ビル選定からオフィス構築、サテライトオフィス導入、リモートワーク促進まで、総合的な視点から提案いたします。
災害リスクを踏まえたオフィス戦略は企業の継続性に直結します。オフィス戦略を見直したいとお考えなら、ぜひ以下からサービス詳細や事例集をご覧ください。
>>MACオフィス「WEOマネジメント」のサービスページはこちら
>>「オフィスコンサルティング事例集」の資料ダウンロードはこちら
>>無料のオフィス診断はこちら
東日本大震災を機に耐震性強化を目的としてビル建て替え・移転を検討しておられたサカモト・ダイテム株式会社様には、働き方の細かいところまでをお伺いし、ご意向をお聞きした結果、新たな空間づくりのご提案ができました。参考にご覧ください。
>>サカモト・ダイテム株式会社の事例はこちら
まとめ
BCPは企業の事業継続に不可欠であり、定期的な見直しとオフィス戦略の最適化が重要です。耐震性や非常用電源、リモート体制など多角的に備え、災害時の被害軽減と迅速な復旧を実現しましょう。
 オフィス戦略
オフィス戦略
 オフィス戦略組織づくりワークスタイル
オフィス戦略組織づくりワークスタイル
 オフィス戦略
オフィス戦略
 オフィス戦略組織づくり
オフィス戦略組織づくり
 オフィス戦略ワークスタイル
オフィス戦略ワークスタイル
 オフィス戦略
オフィス戦略