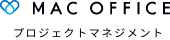新規事業が軌道に乗るかどうかは、参入する市場選びに大きく左右されます。顧客のニーズや競合状況、自社の強みを的確に見極められれば、成功の可能性を高められるでしょう。今回は、新規事業の狙い目を判断するポイントや見つけ方、実際の成功事例までをわかりやすく紹介します。
新規事業の狙い目を判断するポイント

新規事業を軌道に乗せるためには、より「勝ちやすい」分野を見極めることが肝要です。ここでは、その判断のポイントを解説します。
ポイント1|顧客ニーズが高いか
新規事業を検討する際は、まず「顧客ニーズの高さ」を見極めることが重要です。顧客が日常的に抱えている課題や不満に対し、解決策となる製品やサービスを提供できれば、事業の成功確率は高まります。
特に、現時点でニーズが明らかに存在しているにもかかわらず、まだ十分に商品やサービスが提供されていない分野は大きなチャンスです。
また、今はニーズが小さいように見えても、将来的な社会変化やライフスタイルの変化によって需要が拡大する可能性もあります。例えば、高齢化やデジタル化の進展に伴い、新たな課題や要望が生まれるケースも少なくありません。
さらに、安定したユーザーニーズが長期的に見込める市場は、継続的な収益基盤を築きやすくなります。市場の成長性と顧客の本質的な課題を的確に捉えることが、新規事業の方向性を定める上では欠かせません。
ポイント2|競合が少ないか
市場選びにおいては、競合の少なさも重要な判断基準です。すでに多くの企業が参入している市場では、価格競争や差別化の難しさから利益率が下がりやすく、成長速度も鈍化します。
一方で、競争が激しくない市場は、新規参入でも優位性を確保しやすく、事業の立ち上げから拡大までをスムーズに進められる可能性が高まるでしょう。
特に、まだ十分に開拓されていない「ブルーオーシャン市場」は狙い目です。既存の枠組みにとらわれないサービスや独自の提供価値を打ち出せば、早期に市場のシェアを獲得しやすくなります。
ただし、競合が少ない理由が「需要の低さ」である可能性もあるため、事前に市場規模や将来性を見極めることが不可欠です。競争環境の適切な分析と市場の成長性の見通しをあわせて判断すれば、新規事業の加速につながります。
ポイント3|自社の優位性を発揮できるか
新規事業を成功させるためには、自社の強みを活かせる分野を選ぶことが欠かせません。自社の商品やサービス、技術が特定の消費者層のニーズに合致し、価値を提供できることが大前提です。
そのためには、まず自社の得意分野や保有する独自技術、長年の経験によって蓄積されたノウハウを明確にし、それらをどの市場で発揮できるかを見極める必要があります。
それに加え、他社が容易に真似できない独自性を持たせることが重要です。特許技術や特定顧客との強固な関係、独自のブランド力などは強力な参入障壁になるでしょう。
差別化できる要素を軸に事業を展開すれば、価格競争に巻き込まれにくく、持続的な成長も期待できます。
新規事業の狙い目を見つける方法

新規事業のアイデアは、思いつきだけでは成功につながりません。市場や技術、顧客動向を多角的に分析し、実現可能性の高いテーマを見つけることが重要です。ここでは、具体的な方法を紹介します。
既存事業を見直す
既存事業を見直すことは、新規事業の可能性を広げる有効なアプローチです。自社がこれまでに培ってきた技術やノウハウを応用すれば、まったく新しい製品やサービスを生み出せます。
また、長年取引している顧客やパートナー企業の声を反映すれば、ニーズに合致したサービスを構築できるでしょう。既存の資産や関係性を活かせば、ゼロから立ち上げるよりも効率的に事業拡大が可能です。
さらに、自社の強みを活かすことで競合との差別化が図れ、安定した成長基盤を築けます。新規事業を模索する際は、まず現状の事業を丁寧に分析し、活用できる要素を見極めることが重要です。
関連記事:「事業ポートフォリオとは?メリットや作成方法、最適化のポイントを紹介」
新しい技術をチェックする
新しい技術の動向を常にチェックすることは、新規事業の可能性を広げる上で欠かせません。AI(人工知能)、VR(仮想現実)、MR(複合現実)などのデジタル技術は、すでに多くの業界で注目されており、これらを活用したサービスや製品は市場での競争力を高めやすくなります。
重要なのは、新技術を単独で導入するのではなく、既存のビジネスモデルやサービスと組み合わせることです。
技術の組み合わせによって、従来では不可能だった付加価値を提供できるようになり、新たな市場開拓のきっかけになります。
市場調査をする
市場調査は、新規事業の方向性を決定する上で欠かせません。業界の動向や顧客ニーズは時間とともに変化するため、調査は一度きりではなく定期的に行いましょう。
調査方法には、統計データや販売実績を用いたデータ分析、顧客や見込み客へのアンケートやインタビューなどがあります。
これらを活用することで、表面化していない課題や潜在的な需要を発見できる可能性が高まります。特に、市場の変化点を早期に察知することは、新規事業のチャンスを逃さないためのポイントです。
例えば、消費者の価値観の変化や新しい購買行動の兆しを捉えれば、他社よりも先に市場へ参入できる可能性があります。継続的な情報収集と分析を習慣化し、得られたデータを事業戦略に的確に反映させましょう。
異業種コミュニティに参加する
異業種交流会やオンラインサロン、SNSなどを通じて、自社とは異なる業界の人々と接点を持てば、自分たちの業界だけでは得られない視点や知識を吸収できます。
異業種間のコミュニケーションは、業界の常識や固定観念にとらわれない発想を促し、新しいビジネスモデルやサービスのヒントにつながるでしょう。例えば、製造業とIT業界が交わることで、従来になかった製品のデジタル化や効率化のアイデアが生まれる場合があります。
また、参加者同士で課題や事例を共有すれば、自社の強みを活かせる新たな市場や協業の可能性を発見できるかもしれません。
SNSで市場ニーズをチェックする
SNSは、市場のリアルな声や最新トレンドを把握するための有効な情報源です。消費者が日常的に発信する投稿やコメントからは、既存の商品やサービスへの不満点、改善要望、または新たな関心事を直接キャッチすることができます。
特に、不平や不便さに関する声は、新規事業のヒントになりやすく、まだ解決されていないニーズを掘り起こすきっかけにもなるでしょう。
さらに、SNSは拡散性が高く、話題が急速に広まるため、将来の需要が高まる可能性のあるテーマをいち早く捉えることも可能です。特定のキーワードやハッシュタグを継続的に追跡すれば、流行の兆しを早期に察知可能です。
海外の事例を参考にする
先進的な市場を持つ国や、新しいビジネスモデルが生まれやすい地域では、日本ではまだ浸透していないサービスや仕組みが多数存在します。海外の事例を参考にすれば、国内市場での差別化や独自性を打ち出しやすくなるでしょう。
ただし、そのまま真似をするのではなく、日本の文化や消費者の習慣、市場規模に合わせたアレンジが必要です。
新規事業の狙い目を見つけた事例

新規事業の成功には、的確な市場選びと自社の強みを活かす戦略が欠かせません。ここでは、狙い目を見極めて事業を成長させた企業の事例を紹介します。
スキマバイトサービス|株式会社タイミー
株式会社タイミーは、2018年8月に「すぐ働きたい方」と「すぐ人手が欲しい会社」をつなぐスキマバイトサービスを開始しました。
利用者はアプリから簡単に仕事を探し、面接や登録会なしですぐに働けます。一方、会社側は、急な欠員や繁忙期の人手不足を短時間で補えます。
このように、働き方の多様化や人材確保の課題に応える仕組みを提供することで、急成長を遂げたのです。
化粧品開発|富士フイルム株式会社
富士フイルム株式会社は、写真フィルムの主成分であるコラーゲンが肌と同じ構造を持つことに着目し、その知見を化粧品開発に応用しました。
フィルム開発で培ったコラーゲン研究と高度なナノテクノロジーを組み合わせ、成分を角層まで浸透させる技術を確立しています。
デジタル化によって市場規模が縮小したフィルム技術を活用し、スキンケアブランド「アスタリフト」を展開したことで、異業種からの参入でありながら化粧品市場で確かな地位を築いています。
送迎支援システム|ダイハツ工業株式会社
ダイハツ工業株式会社は、通所介護事業者向けに送迎支援システム「らくぴた送迎」を提供しています。
デイサービスでは、利用者を時間通りに送迎するのが難しく、運行ルートの調整や急な変更対応が職員の負担でした。この課題に対し、らくぴた送迎は最適な運行ルートを自動で作成しつつ、利用者が施設や自宅に到着したタイミングで自動通知することで、利用者の家族も安心できるような仕組みを実現しています。
メンテナンスサポート|ヤマト運輸株式会社
ヤマト運輸株式会社は、長年の配送サービスで培った物流ノウハウを活かし、家電修理のメンテナンスサポートサービスを展開しています。
このサービスは、故障した家電製品を利用者の自宅から回収し、修理完了後に返却するまでをワンストップで対応するものです。
利用者は、修理依頼から返却までの手続きを一括で任せられるため、手間や時間の負担を大幅に軽減できます。
配送のプロとしての迅速かつ安全な取り扱いを強みに、家電修理分野でも信頼を獲得しました。
まとめ
新規事業を成功させるには、市場の選定や競合状況の把握、自社の強みの活用など、多角的な視点で狙い目を見極めることが重要です。顧客ニーズの高さや競合の少なさ、新技術の活用などを組み合わせれば、成長の可能性を高められます。
事業開始にあたってオフィス構築が必要な場合は、「オフィスプランニングサービス」をご検討ください。
>>MACオフィス「オフィスプランニング」サービスページはこちら
>>「オフィス移転プロジェクトの進め方」の資料ダウンロードはこちら
>>MACオフィスのオフィス診断はこちら
関連記事:「新規事業立ち上げが重要な理由とは|流れや成功させるコツも解説」
 経営戦略
経営戦略
 経営戦略
経営戦略
 経営戦略
経営戦略
 経営戦略
経営戦略
 経営戦略組織づくりオフィス戦略
経営戦略組織づくりオフィス戦略
 経営戦略オフィス戦略
経営戦略オフィス戦略