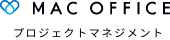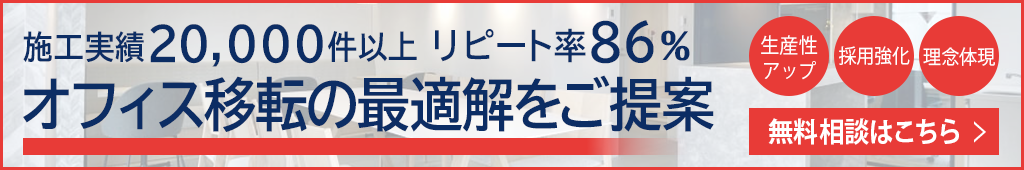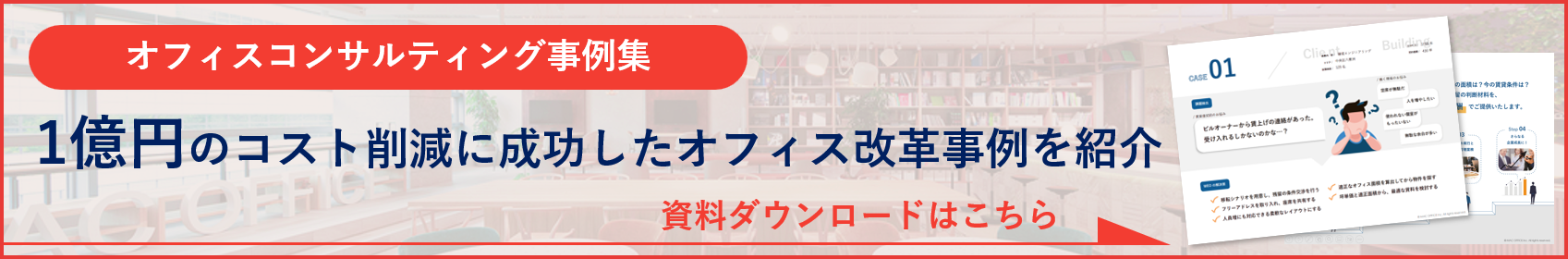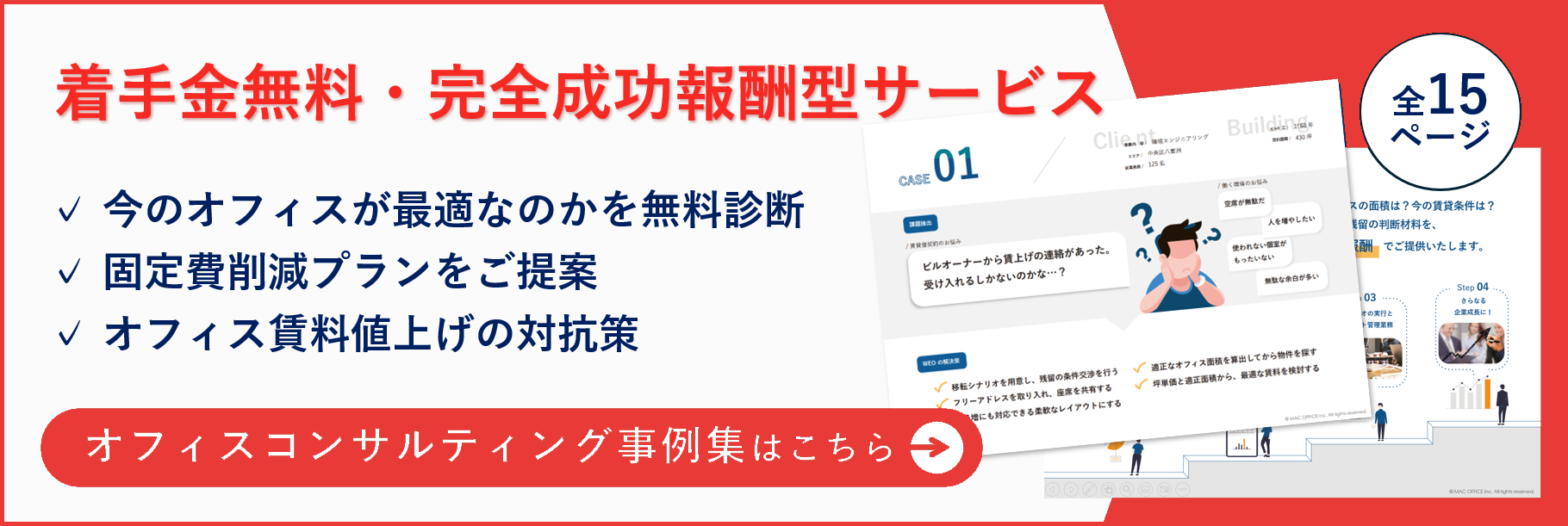人材獲得競争が激しさを増す現代において、採用活動は単なる人員補充の枠を超え、企業の持続的成長を支える重要な経営戦略です。しかし、やみくもに募集を行うだけでは、必要な人材を確保することは難しく、ミスマッチによる早期離職などのリスクも高まります。そこで重要となるのが、体系的な採用戦略の立案です。
今回は、採用戦略を立てることで得られるメリットをはじめ、成功のポイントや具体的な立案手順まで詳しく解説します。
採用戦略を立案するメリット

採用は単なる人材の補充にとどまらず、企業の成長を左右する重要な経営課題といえます。そこで欠かせないのが、事前にしっかりとした採用戦略を立案することです。
明確な戦略があれば、自社の魅力や強みを的確に発信でき、優秀な人材の応募を促すことが可能になります。ここでは、採用戦略を立案することで得られるメリットについて解説します。
応募者数や質の向上が見込める
採用戦略をしっかりと立案することで、市場のトレンドや求職者の志向に沿った訴求が可能になります。自社が持つ強みや魅力を適切に発信できれば、より多くの応募者を集められるだけでなく、関心を持つ層の質も高められます。
結果として、応募の母集団が広がると同時に、企業が求める人材像に合致する候補者と出会えるチャンスが増加します。
内定辞退や入社後のミスマッチを防げる
採用戦略の策定では、自社の特徴や課題、求める人物像を改めて整理することが重要です。自社と高い親和性を持つ人材像が明確になることで、結果的に内定辞退や早期離職が減少し、定着率や生産性の向上につながります。
採用効率アップにつながる
採用戦略を事前に構築することで、採用活動の全体像が明確になり、ターゲットに適した手法や媒体を選定しやすくなります。その結果、無駄な手間やコストを削減できます。
また、戦略に基づいて各施策の効果検証を継続的に行うことで、採用活動の精度を高めることも可能です。
成功する採用戦略の3つの柱とは

採用活動では、「採用ブランディング」「候補者体験」「採用チャネル最適化」の3つが重要です。成功する採用戦略の3つの柱について解説します。
採用ブランディング
採用ブランディングは、企業が自社の魅力や価値観を求職者に伝え、魅力的な雇用先としての認知を高めていく取り組みです。
応募者数の増加ではなく、企業理念やビジョンに共感し、長期的に活躍できる優秀な人材を確保することが目的です。
候補者体験
候補者体験(Candidate Experience)とは、求職者が企業を認知してから選考終了までの一連のプロセス全体を指します。
求人票の情報量・わかりやすさ、エントリー後のレスポンスの早さ、面接官の説明や態度、選考結果の通知方法まで、あらゆる接点が候補者の評価対象です。
採否に関わらず「この企業の選考を受けて良かった」と思ってもらえる対応を積み重ねることで、企業イメージの向上や、再応募・紹介につながる可能性も高まります。
総務省「令和6年版 高齢社会白書」によれば、令和5年(2023年)時点の労働生産年齢人口(15~64歳)は総人口の59.5%にまで低下しており、1995年(平成7年)のピーク時と比べ約10%減少しています。
人材獲得競争が激化する中、企業は「選ぶ側」から「選ばれる側」へと立場を変えつつあるため、候補者一人ひとりに寄り添った体験設計が採用成功のコツです。
出典:総務省「令和6年版 高齢社会白書」
採用チャネルの最適化
採用チャネルとは、企業が求職者と出会うための情報発信経路や接点全般を指します。求人広告媒体、人材紹介会社、自社の採用サイト、SNS、ダイレクトリクルーティング、リファラル(社員紹介)採用など、多様な手段が存在しており、どのチャネルを選択するかで応募者層や採用効率が大きく変わってきます。
採用チャネルの役割は、単に募集情報を掲載するだけでなく、ターゲットとなる求職者に的確に情報を届け、企業とのマッチングを促進し、採用活動全体の効率を高めることです。
例えば、即戦力人材を短期間で確保したい場合は人材紹介会社、企業認知度の向上やカルチャーフィットの高い人材を確保したい場合はオウンドメディアやSNSが適しています。
また、ダイレクトリクルーティングやリファラル採用はコストを抑えつつ、質の高い候補者との接点を築ける手段です。
自社に最適な採用チャネルを選定するには、採用ターゲットを明確に設定し、その行動特性を分析することが不可欠です。採用の目的や人材要件に合わせた柔軟なチャネル戦略を立てましょう。
採用戦略立案の手順

採用戦略は、適切な手順で立案することで精度が上がります。採用戦略を立案する手順について詳しく見ていきましょう。
1.採用戦略を担当するチームを結成する
採用戦略は、配属予定部門の責任者、社員教育を担当する人材開発部門、現場で働く若手社員など、さまざまな立場のメンバーによるチームで立案することが重要です。特定の視点に偏らず、多角的な意見を反映した実践的な戦略が策定できます。
2.採用計画を立てる
会社が今後3〜5年で目指す事業展開や成長戦略を踏まえ、必要となる人材像や人数、採用時期、予算を明確にします。例えば新規事業の立ち上げに伴うエンジニア採用や、海外進出に伴うグローバル人材の確保など、経営方針との整合性が重要です。
3.採用ターゲットを明確にする
採用計画に基づき、どのような人材が自社に最適なのかを設定します。求めるスキルや経験だけでなく、上司やチームとの相性を考慮した年齢層、性格特性(積極性・安定志向など)、価値観なども含めた人物像を具体化します。
4.採用基準を確定する
採用基準が曖昧なままでは面接官ごとに判断がばらつくおそれがあるため、明確で具体的な基準作りが不可欠です。以下は、採用基準を整備するための4つのステップです。
| ステップ | 内容 | 具体例・ポイント |
| 1.評価項目の決定 | 各選考工程で評価する内容を整理 | ・書類審査→業務経験、経験年数、資格保有など・適性検査→チャレンジ精神、協調性、論理思考、正確性など・面接→コミュニケーション力、意欲、仕事観、業務適性など |
| 2.評価基準の決定 | 各評価項目ごとに判断基準を具体化・言語化 | 例「チャレンジ精神」・自ら企画立案・実行できる(経験あり)・企画は立案可能だが実行はサポートが必要・サポートがあれば提案可能 |
| 3.優先順位の決定 | 項目ごとに重要度を設定 | ・部署責任者と事前にすり合わせを行う・評価配点で優先度を反映し、比較検討を容易にする |
| 4.評価基準の周知と面接質問の設計 | 関係者へ評価基準を共有し、質問設計 | ・選考工程ごとに評価担当範囲を明確化・評価に直結する質問例を事前に準備・構造化面接と非構造化面接の使い分け |
5.採用スケジュールを定める
採用計画で定めた採用時期をもとに年間カレンダーを作成し、選考期間・合否通知までのリードタイム・内定者フォローまで見据えたスケジュールを組み立てます。
また、複数の採用チャネルを活用する場合は、それぞれの準備期間も考慮することが大切です。
6.自社の強みを明確にする
自社の採用競争力を高めるためには、自社の強みを客観的に把握しておくことが不可欠です。競合他社との比較分析や、現職社員・新入社員へのヒアリングを行うことで、「なぜ自社を選んだのか」「働く魅力は何か」といったリアルな声を収集できます。
こうした情報を全社で共有し、採用広報や面接で一貫したメッセージとして伝えることで、応募者に安心感や共感を与えることができます。
7.採用方法を選定する
計画段階で確保した予算を踏まえ、採用手法を選定します。若手採用であれば新卒ナビサイト、中途採用であれば転職エージェント、認知向上にはオウンドメディアやSNS活用など、採用ターゲットや目的によって最適なチャネルを使い分けます。
最新の採用手法・市場動向も常に収集し、柔軟に取り入れていく姿勢が重要です。
採用戦略におけるオフィス環境の重要性
オフィス環境は、企業に対する第一印象に大きな影響を与えます。オフィスの立地、内装デザイン、設備の充実度などだけでなく、従業員の表情や雰囲気などからも、企業文化や価値観、従業員への配慮の度合いを読み取ることができます。いわばオフィスは「企業の顔」です。
また、適切なコミュニケーションスペースの配置や集中できる執務エリアの確保、オンライン会議に対応した個別ブースの整備などは、現代の働き方において大きな評価ポイントです。
こうした採用視点でのオフィス環境整備を検討する際、「MACオフィス」では現状の採用情報や今後の採用計画を丁寧にヒアリングし、企業ごとの最適なプランを提案しています。ご興味のある方は以下からご確認ください。
>>MACオフィスのサービスページはこちら
>>MACオフィスのオフィス診断はこちら
さらに「バーチャルオフィス」を作成し、サイト上に掲載することも可能です。WEB上でバーチャルなオフィスを事前に体験してもらうことで、企業の魅力や社風、働くイメージを視覚的に伝えられます。ご興味のある方は以下からぜひ一度ご体験ください。
>>MACオフィスのバーチャルオフィスはこちら
まとめ
採用戦略をしっかりと立案することで、優秀な人材の獲得や定着、採用コストの最適化といった多くのメリットを得ることができます。
社内の関係者を巻き込んだ体制づくりや、自社の強みを明確に打ち出す工夫も重要です。こうした取り組みを通じて自社にフィットする人材との出会いを増やし、人材確保の基盤を築いていきましょう。
 組織づくりワークスタイルオフィス戦略
組織づくりワークスタイルオフィス戦略
 組織づくりオフィス戦略
組織づくりオフィス戦略
 経営戦略
経営戦略
 経営戦略
経営戦略
 組織づくり
組織づくり
 経営戦略
経営戦略