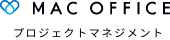心理的安全性とは、対立や非難をおそれることなく、チームの中で自分の意見や疑問を安心して口にできる状態を指します。
たとえ失敗しても責められず、学びや挑戦を歓迎する空気があれば、人は積極的に行動できるようになります。反対に、その安全性が欠けていると、従業員は萎縮し、本来の力を発揮できません。
今回は、心理的安全性が低い職場に見られる特徴や、その状態を放置することによるリスク、改善に向けた具体的な方法について解説します。
心理的安全性が低い職場の4つの特徴

心理的安全性が欠けた職場では、ミスを隠したり意見を飲み込んだりといった萎縮した行動が広がりやすくなります。
ここでは、心理的安全性が低い職場に共通して見られる4つの特徴を解説します。
報連相が徹底されていない
職場の心理的安全性が低いと、従業員が自らミスやトラブルを報告することをためらうようになります。これは、「叱責されるのではないか」「評価が下がるのではないか」といった不安が先立ち、正直に伝えるよりも、黙ってやり過ごすほうが無難だと感じてしまうためです。
結果として、業務の透明性が失われ、重大な問題の見落としや再発を招くおそれもあります。
従業員間のコミュニケーションが少ない
社員同士の雑談や意見交換が少ない職場では、互いの距離感が広がり、気軽に話しかけたり相談し合ったりする空気が生まれません。「自分の意見を言ったことで対立が生まれるのでは」「場の空気を乱すのでは」といった懸念から、発言を控えるようになります。
その結果、助けを求める声が上がらず、孤立したまま悩みを抱える方が増えてしまいます。
自発性・主体性がない従業員が多い
自ら考えて動くよりも、指示されたことだけをこなす姿勢が目立つ職場も、心理的安全性が低い職場の特徴です。自発的な行動によって失敗することや、上司からの評価が下がることをおそれ、できるだけ目立たずにいるほうが安全だと感じてしまいます。
そのため、改善提案や創意工夫が生まれにくく、業務全体の停滞につながる可能性もあります。
新たなアイデアや挑戦に否定的
職場に安心して発言できる雰囲気がなければ、新たなアイデアや挑戦に対しても慎重になりがちです。失敗した場合のリスクを強く意識するため、積極的に取り組もうという姿勢が薄れてしまいます。
現状維持が最も安全であるとされ、従業員が新しいことに取り組む機会を失っていきます。
心理的安全性が低い状態を放置するリスク

心理的安全性の欠如は、単に従業員の働きづらさにつながるだけではありません。放置すれば、業務効率や組織の成長、従業員の定着率など、さまざまな面で深刻な悪影響を及ぼします。
ここでは、心理的安全性が確保されていない状態を放置することによって起こり得るリスクについて解説します。
トラブルへの対処が遅れる
心理的に安心できない職場では、従業員がミスやトラブルを報告しづらくなります。「叱られるのではないか」「責任を問われるのでは」といった不安から、問題を抱えたまま誰にも伝えずに時間が経過してしまいます。その結果、組織としてのトラブル対応が後手に回り、気づいたときには状況が悪化しているというケースも少なくありません。
生産性が低下する
職場に安心して働ける雰囲気がなければ、従業員は自発的に動くことを避け、指示を待つだけの受け身の姿勢に陥りがちです。疑問があっても誰かに聞くことをためらい、不確かな状態で仕事を進めることでミスが増えます。そのフォローに余計な時間や労力がかかるようになれば、生産性の低下も招きます。
企業の成長が鈍化する
新しいアイデアを出すことや、挑戦的な提案をすることに対して、否定されるのではないかという懸念があると、従業員は次第に発言を控えるようになります。「波風を立てないようにしよう」「今のままで良い」といった空気が蔓延し、挑戦や変革が生まれにくくなります。こうした状態が続けば、組織の成長力や柔軟性は次第に失われ、変化の激しい社会に対応できなくなります。
離職率が上がる
日常的に不安やストレスを抱えながら働く職場では、従業員のモチベーションが維持されにくくなります。安心して相談できない、意見を言えない、自分の成長を感じられないといった状況が重なることで、「この職場では長く働けない」と感じる方が増えていきます。こうした状態が続けば、徐々に人材が流出し、組織の中核を担う人材まで離職を考えることになりかねません。
職場の心理的安全性を改善するには

心理的安全性が低い職場では、従業員が日々さまざまな不安を抱えながら働いています。不安が職場に広がると、誰もが様子をうかがいながら最低限の行動しかしなくなり、組織としての成長力が損なわれてしまいます。以下に職場の心理的安全性を改善する方法について解説します。
話しやすい雰囲気をつくる
心理的安全性を高めるためには、相談や質問をしやすい空気をつくることが重要です。特に管理職やリーダーが日ごろから積極的に声をかける姿勢を持つことで、部下との距離感が自然と縮まります。
誰もがミスをする可能性があることを共有し、相談を歓迎する文化を育てることで、従業員の不安は少しずつ解消されていきます。
1on1ミーティングなどコミュニケーションを取る機会を増やす
普段からのコミュニケーションの積み重ねが、心理的な安心感を支えます。1on1ミーティングのように、1対1でじっくり話せる場を定期的に設けることで、従業員の悩みや本音に気づくことができます。日報や簡単なフィードバックの仕組みを取り入れるだけでも、日常の声を拾いやすくなるでしょう。
また、入社間もない社員には、年齢の近い先輩社員が相談役としてつく「メンター制度」の導入も効果的です。
社内コミュニケーション改善についてはこちらも参考にしてください。
「社内コミュニケーションを改善するメリットとは?おすすめの方法も紹介」
会議で特定の従業員に発言が偏るのを避ける
会議の場において、発言が毎回特定のメンバーに偏っていると、他の参加者は自分の意見を言いづらく感じてしまいます。新人や非正規社員など、立場が弱いと感じている方ほど「自分が話して良いのだろうか」とためらうことが多いものです。
そのような空気を改善するには、ファシリテーターが意識的に発言を促す必要があります。「〇〇さんはどう思いますか?」と個別に問いかけることで、全員が安心して意見を出せるようになります。
「心理的安全性の高い職場とは?メリットや環境づくりの方法を紹介」
心理的安全性の担保にはオフィス環境も重要
職場の心理的安全性を高めるためには、制度やコミュニケーションの工夫に加えて、オフィスそのものの環境づくりも欠かせません。働く空間が快適で、リラックスできる場所や話しやすいスペースが整っていれば、従業員同士の距離が自然と近づき、日常の対話や相談も活性化します。
ここでは、企業事例を交えながら、心理的安全性の観点から効果的なオフィス環境の整え方を紹介します。
リフレッシュスペースを作る
リフレッシュスペースは、社員が休憩を取ったり気分を切り替えたりするための空間です。ゆったりとした雰囲気の中で一息つくことができるため、精神的な緊張がやわらぎ、生産性の回復にもつながります。また、部署や役職の垣根を越えて、偶然の会話が生まれる場にもなり、社内のコミュニケーション活性化にも寄与します。
例えば、株式会社ヒューマンテクノロジーズ様では、オフィス内にカフェカウンターやファミレス型のブースを設置することで、従業員同士が気軽に立ち寄り、自然と交流できる空間を整えています。
個室・半個室のスペースを作る
心理的な安心感を得るには、誰にも聞かれずに本音で話せる空間の存在も重要です。1on1ミーティングやセンシティブな話題を扱う場では、周囲の目や耳を気にせず話せる個室や半個室の設置が効果的です。
スターティアホールディングス株式会社様では、個室の会議室に加え、囲われたファミレスブースを導入することで、従業員が安心して話せる場所を用意しています。さらに、ラフな素材感を取り入れたインテリアデザインにすることで、かしこまりすぎないリラックスした雰囲気を演出しており、初対面の相手とも自然に会話がしやすくなるよう工夫されています。
まとめ
心理的安全性は、従業員が自らの意見や気持ちを安心して表現できる環境を整えることで育まれます。そのためには、日常的なコミュニケーションの見直しやミーティングの仕組みづくりに加え、オフィス環境そのものにも目を向けることが欠かせません。
心理的安全性の向上は、個人の働きやすさだけでなく、組織の生産性や人材定着率といった経営課題の改善にも直結します。
こうした視点から、オフィス戦略を経営の一手段として取り入れたいとお考えの方には、MACオフィス「WEOマネジメント」の活用をおすすめします。WEOマネジメントは、オフィス移転や現在のレイアウトの見直し、サテライトオフィスの活用など、複数のシナリオを比較検討した上で最適な提案を行うサービスです。ファシリティマネジメントの観点から、従業員の働きやすさやコミュニケーションの円滑さなど、心理的安全性にも配慮したオフィス戦略を提案いたします。サービス詳細や、事例資料については、以下のリンクからご確認ください。
>>MACオフィス「WEOマネジメント」のサービス詳細はこちら
>>MACオフィス「WEOマネジメント」事例の資料ダウンロードはこちら
また、自社のオフィスにどのような課題や改善ポイントがあるのかを明確にしたい方は、無料で受けられる「オフィス診断」もご活用ください。
>>MACオフィスのオフィス診断はこちら
 組織づくりワークスタイルオフィス戦略
組織づくりワークスタイルオフィス戦略
 組織づくりオフィス戦略
組織づくりオフィス戦略
 組織づくり
組織づくり
 組織づくりオフィス戦略経営戦略
組織づくりオフィス戦略経営戦略
 組織づくり
組織づくり
 組織づくり
組織づくり