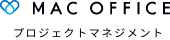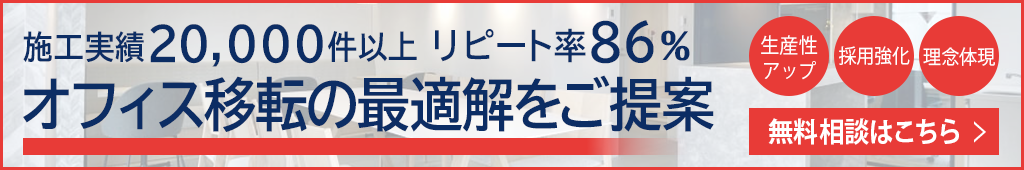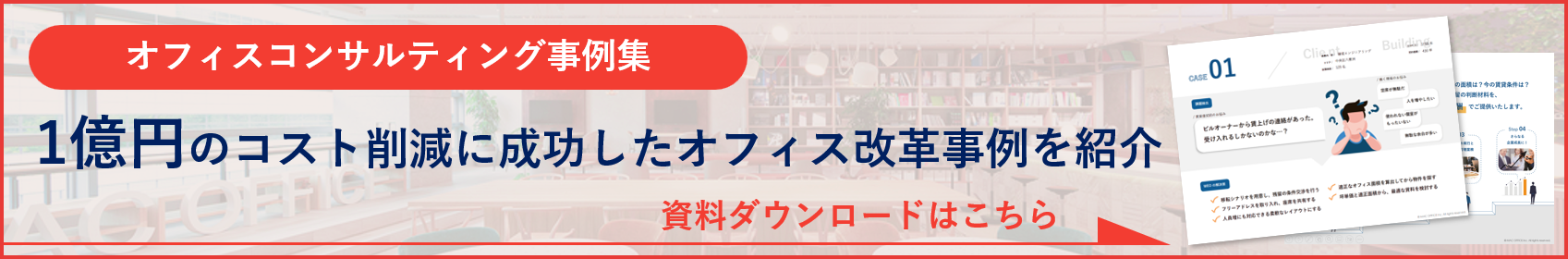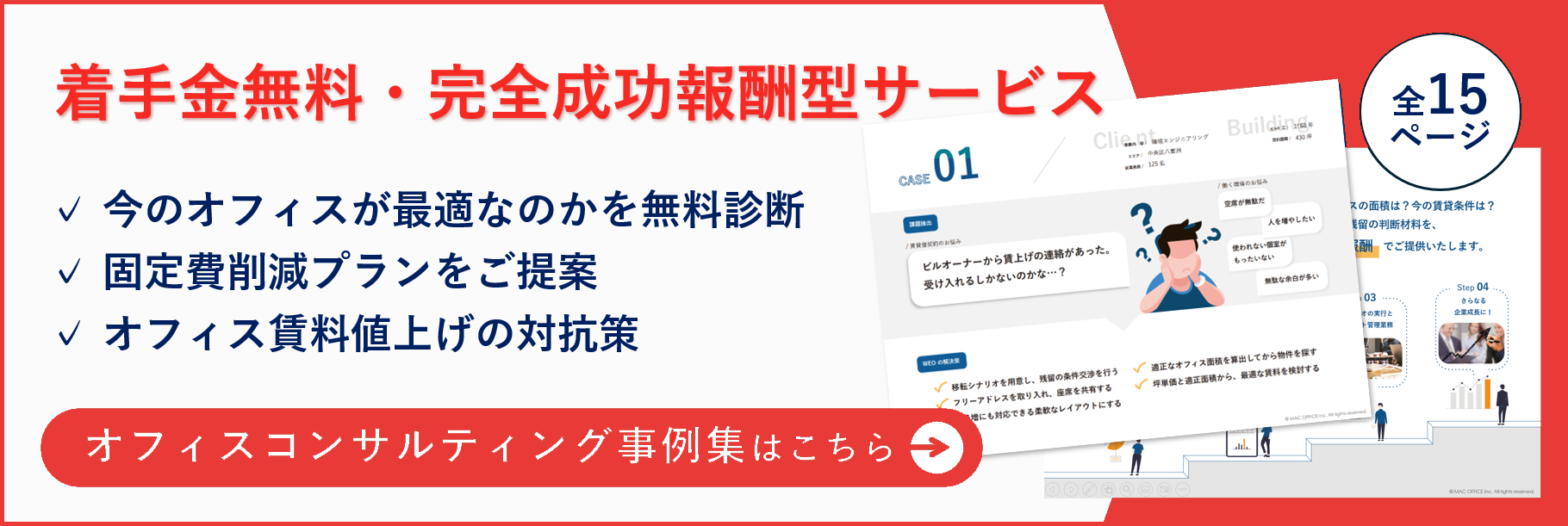近年、企業の社会的な存在意義を中心に据えるパーパスドリブンな組織のあり方が、企業経営の閉塞感を打破する手段として注目されています。
パーパスドリブンを経営に取り入れることで、意思決定が迅速化するだけでなく、社会貢献と持続可能な成長の両立や従業員の帰属意識向上なども期待できます。
今回は、パーパスドリブンの意味や重要性を踏まえ、パーパスを適切に設定し、浸透させる方法のほか、オフィス戦略によってパーパスを実現する方法についても解説します。
パーパスドリブンとは

そもそも「パーパスドリブン」とは何を意味するのでしょうか。言葉の意味とパーパスドリブンな組織づくりが企業にもたらす効果を解説します。
パーパスドリブンの意味
「パーパスドリブン(purpose driven)」は、日本語で直訳すれば「目的に駆動された」という意味をもつ英語です。
企業経営における「パーパス」とは、単なる目的ではなく、自社の社会的な存在意義を言語化したものです。「どのような価値を提供するために存在しているのか」「社会でどのような役割を果たすのか」などの問いかけに対する答えに相当します。
また、ビジネス用語としての「ドリブン」は、「データドリブン」のように「~を起点とした」「~によって推進される」などの意味合いがあります。
つまり「パーパスドリブン」とは、自社の存在意義を軸に、事業戦略や従業員教育、ブランディングなどの企業活動全般が展開されることを意味します。
パーパスドリブンがもたらす効果
パーパスドリブンな組織のあり方は、多岐にわたる効果をもたらします。
経営面では、パーパスが明確な判断軸となるため、目先の利益にとらわれず、一貫性のある質の高い意思決定が可能となります。また、意思決定の迅速化により、機会損失の減少にもつながるでしょう。
人材育成の面では、従業員のロイヤリティや自律性の向上にもプラスの影響を及ぼします。会社の存在意義が明確になれば、従業員の働きがいやモチベーションの源泉となるためです。
パーパスを通じて行動指針がより明確になれば、従業員の自発的な行動が増え、パフォーマンスも高まります。また、パーパスを共有することで、企業全体の一体感が高まる点もメリットです。
さらに、社会との関わりにおいても大きな役割を果たします。パーパスは、従来の利益追求主義に代わり、持続可能な社会への貢献を目指すESG(環境・社会・ガバナンス)の観点からも重視される概念です。
社会問題の解決を目指すパーパスは、企業の社会貢献と持続可能な成長を両立させるだけでなく、顧客や株主などのステークホルダーから選ばれるためにも今や欠かせない要素といえます。
パーパスの設定方法

パーパスドリブンを企業経営で実現するには、自社の社会的な存在意義をパーパスとして明確に定めていることが前提です。続いて、パーパスの設定方法をステップごとに解説します。
1.パーパスを明確にする
まずは、社会における自社の存在意義を深く掘り下げます。パーパスを発想する際のポイントは、Whyを起点に考えることです。
What(何をするのか)やWhere(どこを目指すのか)ではなく、Why(事業を行う理由)を起点に考えることで、自社の存在意義が明確になります。適切なパーパスかどうかの判断基準は、以下の4点です。
・社会課題の解決に貢献できる内容か
利益追求に偏ることなく、自社の事業を通じてどのような社会課題の解決に貢献できるか検討します。
・自社の強みが軸となっているか
競合他社とは違った事業特性、独自の技術や専門性などを活かせる内容かを考えます。
・自社で実現可能か
理想論で終わらず、現実的に実現できる内容かを見極めます。
・従業員が当事者意識をもてる内容か
従業員にとって「自分の仕事がパーパスにつながっている」と感じられるか、従業員の共感を得られる内容になっているかを検討します。
上記の4点は必ずしも整合性が取れるとは限りません。枠にとらわれず、自由な発想で自社ならではのパーパスを検討することが大切です。
2.パーパス・ステートメントを作成
次の段階では、言語化したパーパスをまとめた「パーパス・ステートメント」を作成します。
パーパス・ステートメントのポイントは、パーパスを実際の事業や業務と結びつけ、行動指針として活用できるレベルまで落とし込むことです。
具体的には、How(どのように実現するのか)にあたる「バリュー」もあわせて記載すると良いでしょう。バリューとは、従業員の取るべき行動や判断の基準となる価値観や行動指針のことです。
パーパスをバリューと結びつけて伝えることでパーパスへの理解がさらに深まり、従業員の自発的な行動を促せます。
3.効果を測定して改善する
パーパスを策定して終わりにせず、継続的に効果を測定して改善することが重要です。まずは、パーパス・ステートメントを社内外に共有し、顧客、株主、従業員などのステークホルダーにパーパスが広く伝わるように努めましょう。
効果測定の指標には、財務指標をはじめ、事業がもたらした変化を測定するインパクト評価のほか、パーパスの認知度調査やエンゲージメント調査などがあります。
これらの効果測定を通じて、パーパスドリブンな取組の進捗や企業に与える影響力を定期的に評価し、必要に応じてパーパスの改善を図ります。
パーパスを浸透させる方法

パーパスを実現させるには、従業員がパーパスを「知っている」だけでは不十分です。パーパスの重要性を理解し、従業員が自発的な行動を起こせる状態を目指す必要があります。続いて、従業員がパーパスを体現するための効果的な取組について紹介します。
社内報で発信する
策定したパーパスを社内報で発信すれば、従業員のパーパスへの認知や理解、共感を高められます。
社内報では、パーパスの内容だけでなく、策定に至るまでの経緯、経営陣がパーパスに込めた想い、従業員のインタビューなども掲載すると良いでしょう。パーパスの重要性への理解と納得感が深まり、従業員の自発的な行動へとつながります。
ワークショップを実施する
パーパスの浸透を目的としたディスカッションやグループワークの機会を用意しましょう。パーパスと業務の接点を考える時間や参加者同士の意見交換を通じて、各従業員がパーパスを自分事として捉えられるようになります。
部署の垣根を越え、パーパスや会社の未来像について語り合う時間は、企業の一体感の醸成や社内コミュニケーションの活発化を図る上でも効果的です。
社内アンケートを定期実施
パーパスの浸透度を把握するため、定期的に社内アンケートを実施しましょう。「自社のパーパスについて十分理解しているか」「業務とのつながりを感じられるか」などの項目を設定し、現状を確認します。
アンケートの結果、パーパスの浸透が不十分な場合は、企業全体で戦略を見直し、原因を分析した上で周知方法やワークショップなどの改善を図ることが求められます。
パーパスドリブンには「オフィス」も重要な要素
オフィス戦略を見直すことで、自社のパーパスに共感し、従業員が自ら行動するパーパスドリブンな企業に近づける可能性があります。詳しくみていきましょう。
パーパスドリブンに必要な「自律的な働き方」を促進
パーパスドリブンな企業を実現するには、自社のパーパスに基づき、自律的に動ける従業員を育成する必要があります。その際に重要な役割を果たすのがオフィス戦略です。
例えば、固定席を決めないフリーアドレス、始業と終業の時間を自由に決められるフレックスタイムなどの制度は、柔軟な働き方を促進し、従業員の自律性を養います。
そのほか、経営戦略に応じて働く場所を最適化する「ワークプレイス戦略」や、ライフスタイルに合わせた働き方の調整なども、従業員の自律性を高める上で有効です。
このようなオフィス改革は、自律性を尊重した働き方のサポートを通じて、企業がパーパスドリブンな組織への進化を促進します。
ワークプレイス戦略やウェルビーイングを高める働き方、従業員満足度を向上させる方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
「ワークプレイス戦略とは?注目されている背景や考え方を解説」
「ウェルビーイングを高める方法とは|働き方やオフィス環境など多方面から解説」
「従業員満足度(ES)の向上方法とは?注目される背景や期待できる効果も解説」
パーパスドリブンを支える「オフィス戦略」のご相談なら
自社のパーパスや経営戦略を踏まえ、戦略的にオフィスを改革したいとお考えの方は、MACオフィスにご相談ください。MACオフィスでは、企業にとって最適なオフィス環境を整備するためのコンサルティングを行っています。
まずは専任の担当者が、パーパスドリブンを進める中で生じる働き方やオフィス環境などの課題をお伺いします。その上で、オフィスのレイアウト変更や改装、移転など複数の選択肢を比較しつつ、適切な戦略をご提案します。興味のある方は以下で詳細をご確認ください。
>>MACオフィス「オフィスコンサルティング事例集」資料ダウンロードはこちら
>>MACオフィスのオフィス診断はこちら
まとめ
パーパスドリブンな組織づくりは、社会貢献と持続可能な成長を両立しつつ、企業の価値を高められる戦略です。パーパスの策定は、事業における意思決定の軸を明確にできるだけでなく、従業員の帰属意識やパフォーマンスの向上も期待できます。
ただし、パーパスドリブンな組織づくりを成功させるには、パーパスの設定のほか、社内報やワークショップによる社内浸透などの一貫した取組が求められます。
パーパスドリブンな体制の構築に向けて従業員の自律性の向上を図りたい場合は、オフィス戦略も検討してみると良いでしょう。
 オフィス戦略
オフィス戦略
 組織づくりオフィス戦略ワークスタイル
組織づくりオフィス戦略ワークスタイル
 オフィス戦略
オフィス戦略
 オフィス戦略組織づくり
オフィス戦略組織づくり
 経営戦略
経営戦略
 経営戦略
経営戦略